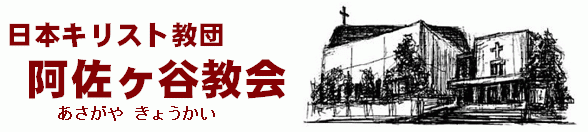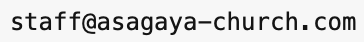◇アーマスト大学で学び始めた若き内村鑑三は、自分の心に潜む罪に悩み、自分が伝道者になる資格があるのかどうか思い悩む。シーリー学長の「なぜ、十字架の上で君の罪を赦されたイエス様にお委ねすることをせず、自分の内側ばかりを見つめているのか。」という言葉で、鑑三は罪から解放され、宣教を生涯の使命としたのである。
◇イエス様の弟子たちも同様であった。主イエスを、イスラエルをローマの支配から解放してくれるメシアであると信じ、従った。ところが、そのイエス様は十字架に引かれて行く。希望を打ち砕かれた弟子たちはイエス様を見捨てる。その彼らに復活の主イエスが現れたと福音書は伝える。十字架の様々な意味のうち、最も重要なのは罪の贖いとしての十字架である。贖いとは、債務奴隷となった者を、親族が身代金を払って解放するようなことである。第2イザヤは「主の僕の詩」で罪を負債と見て、ひとりの僕の苦難により私たちが罪から解放されたと言う。これはキリストの予型である。
◇十字架には理不尽さがある。薬害、公害病、犯罪被害などの理不尽さがこの社会にもある。被害が出て初めて予防策が講じられることがよくある。私たちが生かされているということ自体が、実はそうした多くの人たちの苦難や犠牲の上に成り立っている。イエス様の十字架のもとには、無数の小十字架が立ち並んでいるのではないかと思わされる。ここに十字架のもつ社会性がある。
◇十字架の死の後、三日目に主イエスは復活した。十字架は希望のしるしである。「我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか」という言葉は絶望のように響く。しかしその奥には希望の種が埋め込まれている。神が下した故なき苦しみの中で、なお神にしがみつく、確たる信仰がある。自分の罪や弱さに打ちひしがれる時、不合理極まりない苦難にあえぐ時、イエス様の十字架をしっかりと仰ぎ見つつ、与えられた地上の歩みを進めて行こう。